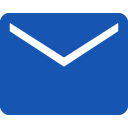【佐渡生き物語】日本の国鳥キジの知られざる秘密に迫る
新潟県佐渡島の生き物を紹介する映像記者、大山文兄のフォトエッセイの第21回目は、Japan 2 Earthのロゴにもなっている日本の国鳥、キジの生態を紹介します。

This post is also available in: English
国の特別天然記念物のトキを撮影するために東京から新潟県佐渡に移住して4年。我が家の庭で、まさに我が物顔に生活する日本の国鳥キジにフォーカスした。
飛ぶのが苦手
「ケンケーン」
最近、けたたましい鳴き声で朝の撮影に出る前の貴重な眠りを妨げるのがキジだ。
キジは飛ぶことが得意ではなく畑や葦などの繁みにいる。オスは長い尾羽を持ち、身体はクジャクのような緑で光沢があり、顔は鮮やかな赤で目立つ。繁殖期(4月~7月)には顔の赤の肉腫が大きくなりハート型に見える。縄張りを誇示するため鳴き声をあげ、その後、ドラムのように羽根をふるわせる。
一方、メスは茶褐色で地味。この時期、オスの近くにいるが隠れているため見つけるのはとても難しい。メスは地面のくぼみに巣を作り、卵を孵化させる。育てる役目のメスが目立たない色なのは自然の理といえるだろう。今回、メスをオスと同じ写真に撮影することに成功した。

佐渡固有のキジはどこに?
トキの取材で世話になっている金子良則獣医師によると、日本には4種の亜種があり、佐渡を含む本州北部のキタキジ、本州中部・四国などのトウカイキジ、キュウシュウキジ(本州南部、九州など)、シマキジ(種子島など)に分類される。その中でも、佐渡のキタキジは大型で尾羽にスジがないのが特徴だった。しかし、国鳥でありながら狩猟が許されていることから、各地で人工増殖や放鳥が行われ、亜種間の差異が不明瞭になってきたという。私が撮影したキジには、佐渡固有の特徴はなかった。最近は報告例がなく、既に絶滅してしまった可能性がある。

国島に選ばれたキジ
キジは本来臆病だがオスは繁殖期、勇猛になる。縄張りに侵入したオスを見つけると戦いが始まる。撮影していると、畑から2羽が急に高く飛び出し、空中で戦い始めた。一瞬で勝負がつき、姿を消してしまった。メスの取り合いなのだろう。キジは一夫多妻でオスは複数のメスと交尾する。しかし、育児には協力しない。メスは母性愛が強く、巣を守るため火事で火の手が迫っても、草刈り機が近づいても逃げず、犠牲になることがよくあるという。

日本固有種で本州から九州まで広く観察され身近であることや、日本の古典「古事記」や童話「桃太郎」などにも登場、日本鳥学会は1947年、キジを日本の象徴として国鳥に指定した。面白いのは国島とされながらも狩猟が許されていることだ。
自宅の窓越しで、庭をパトロールしているオスのキジと目線が合うことがある。堂々としたものだ。キジにしてみれば侵入者は私なのだろう。

「佐渡生き物語」フォトエッセイをもっと読む。

大山文兄(おおやま・ふみえ)産経新聞社写真報道局で新聞協会賞を2回受賞。新聞社時代に11年間にわたり、トキの野生復帰を取材。2020年に退社して佐渡島に移住、農業に従事しながら、トキをはじめとする動物の写真を撮り続けている。映像記者として佐渡の魅力を発信中。インスタグラムでフォローしてください。
This post is also available in: English