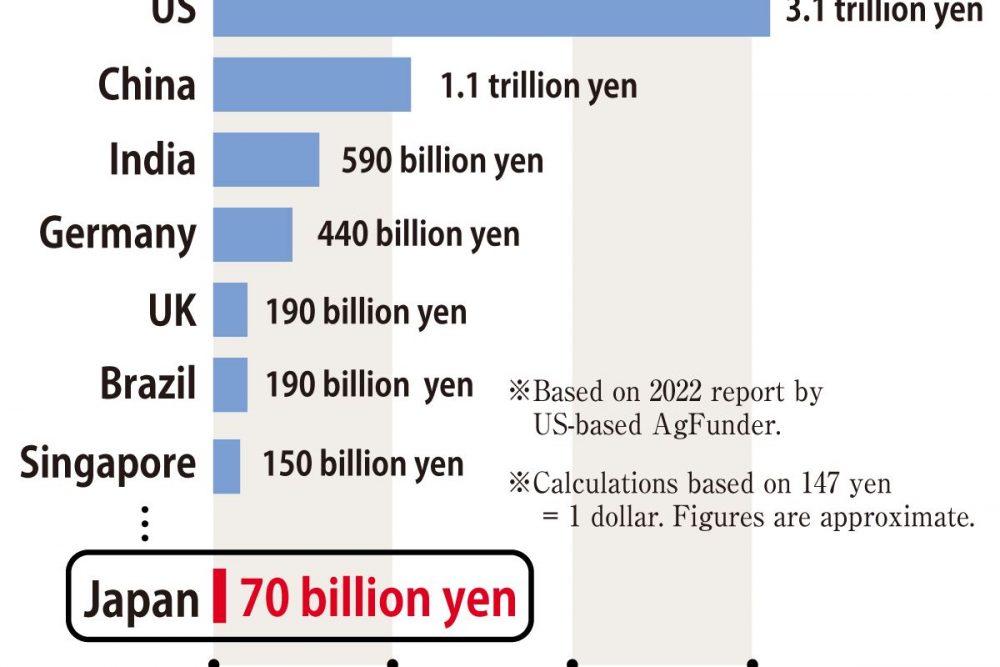【いつかきた道】「水」を通じて自治体が国際貢献
日本の過去の経験をラオスで生かすさいたま市の職員

This post is also available in: English
水道の蛇口を開ければ24時間水が出て、そのまま口にすることができる日本。この日本のあたりまえが世界では通用しない。
「水が出るようになったと喜んでもらい、水道の重要さを改めて認識させてもらいました」
ラオスに水道事業の支援のため、2018年からコロナ禍も含め約3年間にわたって技術協力プロジェクトのチーフアドバイザーとして支援してきた、さいたま市水道局の職員、園田圭佑さんは振り返る。
さいたま市のラオスの水道事業協力は今から30年前の1992年に遡る。ラオスで水道に対してどのような支援ができるかという国の調査事業に声がかかったことがきっかけに、同市は継続的に専門家を派遣してきた。
ラオスの水道普及率は全国で26%。乳児や幼児死亡率は日本の約30倍と高く、水の影響は大きい。
園田さんが行っているのは、水道事業の維持や管理体制を強化する分野だ。
「日本で、水道水が濁ればニュースになりますが、ラオスでは珍しいことではありません」と園田さん。水源の濁りを取り除くために薬品を使うが、ラオスは日本のようにその処理が自動化されておらず、手作業の場合が多い。日本のノウハウに始まり、配水・給水の施工基準の確立や管理能力の向上のための指導にあたってきた。
初めてのラオス
忘れられないのは、中国との国境に接するポンサリー県に行ったことだ。首都ビエンチャンから飛行機と車を乗り継いでも一日半かかる。遠方にある山間地の小さい県のため支援が届きにくく、専門家の訪問はこれまでほとんどなく、驚くほど歓迎してくれたという。
集落は歴史がある急な勾配の石畳の街路をはさみ、昔ながらの家屋が残る。観光資源になりえるため、石畳を掘削などで破壊しないように水道管を石畳下に入れるのではなく、民地の両側に設置するように指導した。
埋設後は見えなくなる水道管は、維持管理のために工程一つ一つの写真撮影が重要で、日本ではあたりまえだが、ラオスでは手間もかかるため、撮影していないことがほとんどだった。
「ポンサリー県では管理運用上難所が多いため、工事での写真撮影が必須。写真撮影の重要性を理解してもらいました」と話す。
リモートで協議や指導もできるが、実際に現地で顔を見て行う「目に見える支援」の重要性を実感したという。
日本が通ってきた道
水資源に恵まれ、水道先進国である日本だが、歴史を振り返れば、最初から優等生だったわけではない。1800年代後半、欧米との交易がきっかけに貿易港に指定された横浜や神戸を中心に、コレラやチフス、赤痢などの消化器系の伝染病が蔓延する。このため、横浜では、英国人技師の指導のもと、資材を英国から輸入。高圧送水、ろ過浄水、常時給水といった近代水道は横浜市で始まった。衛生的な水は、生命に直結する。水道の整備が進んだことから日本の乳児の死亡数は大幅に減少した。
その一方で、第二次世界大戦後まで水系消化器系伝染病の患者数は減らなかった。これが劇的に減少するのは、連合国軍総司令部(GHQ)が対日占領政策で、塩素消毒を徹底させたことが大きい。
水道普及率は1960年代では53%超だったが、都市だけではなく、地方など人口が少ない地域にも国をあげて水道が引かれ、80年代で90%超えた。現在は98%とほぼ100%に及んでいる。
「水源が乏しく、施設もなく、資金も不十分で人材も足りない」―。こうした途上国の悩みは、水道先進国の日本がかつて、通ってきた道でもある。
「顔」の見える支援
世界の約20億人が安全に管理された飲み水にアクセスできていない。SDGsは2030年までに全ての人が安全な水を得られる社会の実現をターゲットにしている。
浄水場建設や水道管の整備といったインフラ建設は、国際協力機構(JICA)の政府開発援助(ODA)や世界銀行、アジア開発銀行(ADB)を通じた資金で行われることが多い。日本もこれらの機関に資金を供与しているが、それに加え、取り組んでいるのは人材育成や管理能力のアップなどのソフト面での「草の根」の技術協力支援だ。

欧州などの宗主国の途上国支援では、プロジェクトが終わった後のフォローがなく、せっかくのインフラもその後の維持管理でつまずくことが往々にしてある。日本もインフラ整備を行っているが、運営の継続ができるように各自治体の水道事業体の職員が現地で指導にあたる。「日本の支援で建設」といったジャパンフラッグの標識も大切だが、人を通じたコミュニケーションを通じた支援こそ、真の「顔が見える支援」に思う。
園田さんがラオスに派遣された当時、家族には6歳を筆頭に4歳、1歳の3人の子どもを抱え、単身赴任となった。家族がいない寂しさや停電がよく起きるなど、慣れない生活に苦労したこともあったが、水道事業を通じて知ったラオスが大好きになった。帰国後に誕生した4番目の子どもも一緒に、家族で再びラオスに訪問したいという。
This post is also available in: English