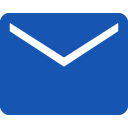【佐渡生き物語】新築、リフォーム…トキのおうち事情
新潟県佐渡島の生き物を紹介する映像記者、大山文兄のフォトエッセイの第20回目は、国の特別天然記念物、トキの”おうち事情”を紹介します。

This post is also available in: English
雪も解け、新潟県佐渡島にも春がやってきた。国の特別天然記念物、トキが巣作りのため忙しく飛び回る姿が確認されている。巣作りでも個性が現れている。
営巣林内で連日、巣作り
寒さも緩み、日の出時刻も徐々に早くなってきた。
日課であるトキの撮影に出かけると、巣材にするための枝を何度も運んだり、巣の中に敷き詰めるために柔らかな枯草などを運んでいるトキの姿が観察されるようになった。
私のトキの撮影場所はトキの密度が1、2の高さの営巣林だ。佐渡に移住して今年の春で5年。毎年同じ営巣林を観察するといろいろなことが見えてくる。前年、ヒナが巣立ちした営巣林には、翌年に繁殖に失敗したトキのペアが集まってくることに気付いた。
人気の「枝」物件
人間の世界でも人気の駅や間取りのマンションはすぐに売れてしまうのと同じで、トキの巣作りも昨年繁殖に成功した巣の跡地は”一等地”となり、その場所を死守するため、同じペアが交代で見張りながら巣作りしている。また、昨年使われた巣を枝で補強して”リフォーム”するペアもいる。せっかく巣材をくみ上げたのに強風で崩れてしまう巣も少なくない。
営巣林にたくさんの樹木があるが、実は巣に適した枝というのはそんなに多くはない。なぜなら、トキの成鳥の重さは1.5〜2kg。ペアだけでも約3kgを超える。仮にヒナが3羽誕生したとすると、巣立ち時には親と同じぐらいの重さになるため、親鳥2羽と幼鳥3羽で計7kgを超える。この重さに耐えられるしっかりとした枝が必要になる。

※佐渡では、トキの繁殖に影響があるため巣には近づかないルールがある。巣が写っているのは環境省提供のため。
以前のコラムでも紹介したが、スズメなどの鳥は冬の厳しい環境下で、集団になって天敵に対抗しているが、トキは集団になることでカラスなどの天敵をおびき寄せてしまうなどのリスク要因が大きく、集団で繁殖するメリットはないと言われる。また、営巣林が過密化すると、一本の杉の木の上と下で巣作りしたり、わずか数メートル離れた同じ高さに別の巣ができたり、巣を乗っ取ったり…。これでは静かに卵を温めることも雛を育てることもできない。
擬交尾で存在をアピール
この時期、よく観察されるのが擬交尾だ。巣作りの時期には縄張り意識が高くなり、他のトキを確認すると擬交尾を盛んに行う。

32年間、佐渡トキ保護センターでトキの野生復帰に携わってきた金子良則・獣医師は「野外だけではなく、エサを与えるためにケージに飼育員が入っても擬交尾を行う。一種の示威行為ではないか」と話す。
擬交尾はシロチドリなど他の鳥でも観察されるが、トキのように日常的に観察されていないため、実態ははっきりわからない。
現在、佐渡のトキは約500羽が野外で生息していると推定される。過密状態なため、来年6月に石川県で放鳥されることが決まった。石川の放鳥が成功するためにも佐渡のトキの毎日の生態の観察が欠かせない。

「佐渡生き物語」フォトエッセイをもっと読む。

大山文兄(おおやま・ふみえ)産経新聞社写真報道局で新聞協会賞を2回受賞。新聞社時代に11年間にわたり、トキの野生復帰を取材。2020年に退社して佐渡島に移住、農業に従事しながら、トキをはじめとする動物の写真を撮り続けている。映像記者として佐渡の魅力を発信中。インスタグラムでフォローしてください。
This post is also available in: English