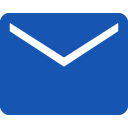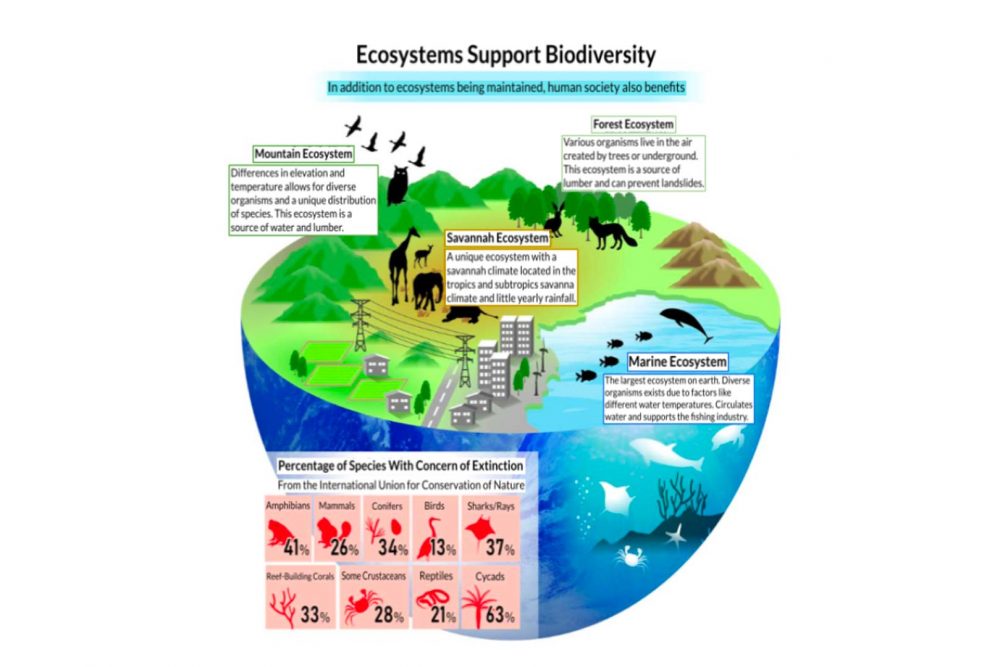【佐渡生き物語】嫌われもののカワウの名人芸
新潟県佐渡島の生き物を紹介する映像記者、大山文兄のフォトエッセイの第25回目は、フン問題などで嫌われ者のカワウの実態に迫ります。

This post is also available in: English
フンや鳴き声で最近、迷惑者とされているカワウだが、かつては数が減り絶滅の恐れもあった鳥だ。今や佐渡でも水辺では必ずと言っていいぐらい見かける。今回はカワウに、カメラのレンズを向けた。
漁の名人
湖や貯水池で、勢いよくカワウがダイビングした後、魚を丸のみして、水しぶきをあげて飛び出していく。潜水時間は長い時には1分を超える。
カワウは空を飛ぶ漁師だ。エサは魚。潜水の深さは1~9mと潜水が得意だ。主に早朝に採食行動を行う。食欲旺盛で、体重1kgあたり262gの魚を食べるという。
普段は群れで行動している。電線にスズメのようにズラリと並び羽根を休めている姿も観察された。重さで、電線が大きくたわみ電線に影響がないか心配になるほどだった。

一時は絶滅の危機に
カワウはペリカン目ウ科に分類され、ヨーロッパやアジア、アフリカ、オーストラリアなど南米以外の大陸とオセアニアに生息、種類は約40にのぼる。日本には4種のウがいる。ウミウと酷似しているが、ウミウの方がカワウより少し大きい。クチバシもウミウは口角で三角形に尖っているが、カワウは尖っていない。頬の白い部分も目の後方に真っすぐ伸びている。(トップ写真参考)。
環境省によると、カワウは日本全国に分布していたが1960年代以降、河川の改修や干潟の埋め立て、ダイオキシンなどの有害物質の汚染などによって数が減り、コロニーが消失、関東で約7千羽いたとみられるが、1971年には全国で3千羽に減り、レッドデータブックの絶滅危惧に相当する減少率だった。
1980年に入ると、化学物質の規制や水質改善で個体数が増加、コロニー分布が拡大、全国に広がっていった。今や樹木をフンで枯らしてしまったり、住宅地での鳴き声の騒音などが問題になっている。

日常風景に
日本野鳥の会佐渡支部支部長の土屋正起さんによると、佐渡でカワウが観察されるようになったのは、10年前にすぎない。新潟最大の湖、約5平方kmの加茂湖に約2千羽が生息しているという。
本州では、カワウによるアユ漁への被害で漁業者にとって死活問題になっている。加茂湖の漁業は主にカキの養殖やアサリ、ナマコのため、漁業被害の報告はないという。
土屋さんは「今のところ被害の話はないが、カワウの生息数の増加を注視していく必要がある」と話す。
船の上に火をともし、鵜匠がウを操って魚を丸丸呑みしたウから魚を吐き出させる岐阜県長良川の鵜飼漁は夏の風物詩になっている。最初はカワウで漁を行っていたが、今は身体が少し大きいウミウを使っているという。約1300年の歴史があり、国の重要無形民俗文化財に指定されている。
せっかくとった食料を人に横取りされたり、フンなどで嫌われるカワウは受難者といえる。佐渡では幸い、ヒトとの軋轢は起きていない。川辺でぼーっと潜水で羽根を乾かしているカワウはどことなく愛嬌もある。温かく見守っていきたいと思う。

「佐渡生き物語」フォトエッセイをもっと読む。

大山文兄(おおやま・ふみえ)産経新聞社写真報道局で新聞協会賞を2回受賞。新聞社時代に11年間にわたり、トキの野生復帰を取材。2020年に退社して佐渡島に移住、農業に従事しながら、トキをはじめとする動物の写真を撮り続けている。映像記者として佐渡の魅力を発信中。インスタグラムでフォローしてください。
This post is also available in: English